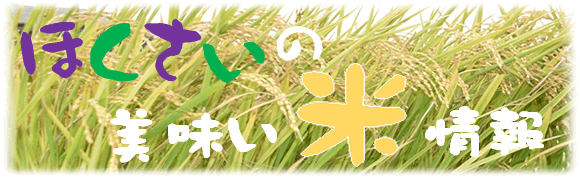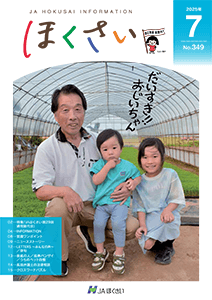梨の春作業が始まりました
JAほくさい管内の加須市騎西地区で4月上旬から梨の花かけ(授粉)作業が始まりました。
4月9日、加須市騎西梨撰果所利用組合の鈴木昭二さん、清香さん夫妻は、梨の白い小さな花が一面に広がる園地で、彩玉の花かけ作業に汗を流していました。
今年は天候に恵まれ、例年通りの作業開始となりました。
鈴木さんは50アールのほ場で「幸水」や「彩玉」、「豊水」、「あきづき」を栽培します。
鈴木さんは、「花摘みと摘蕾、花かけと毎日忙しいが、園地の管理をしっかりと行い、収穫を迎えたい」と意気込みを語りました。